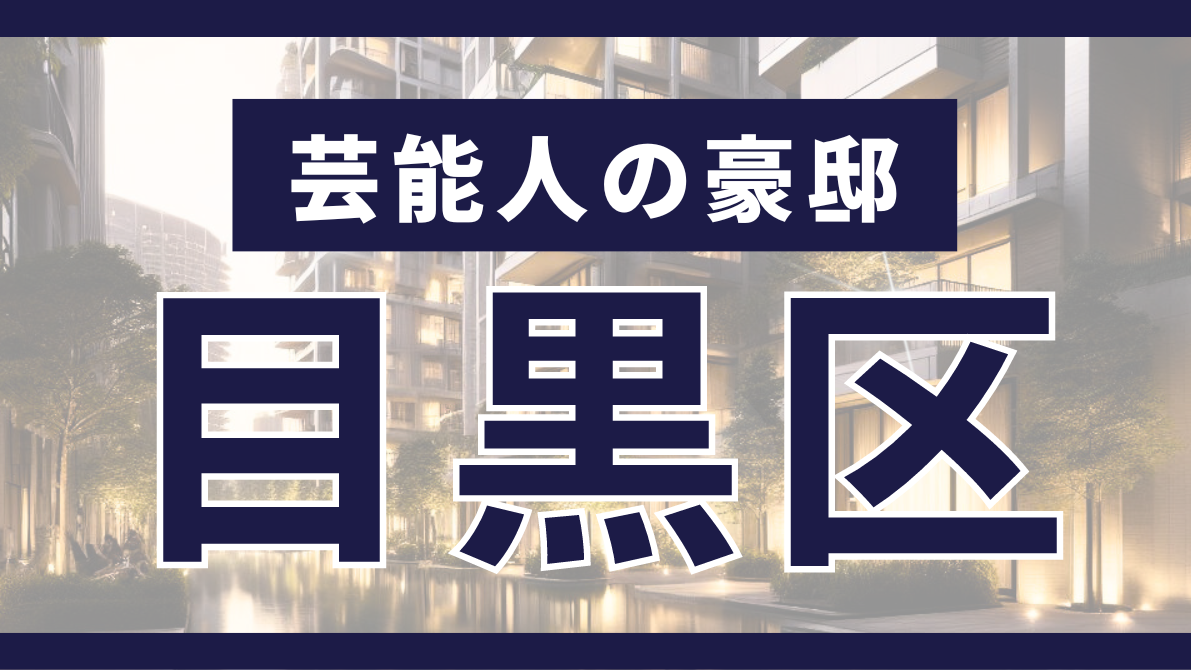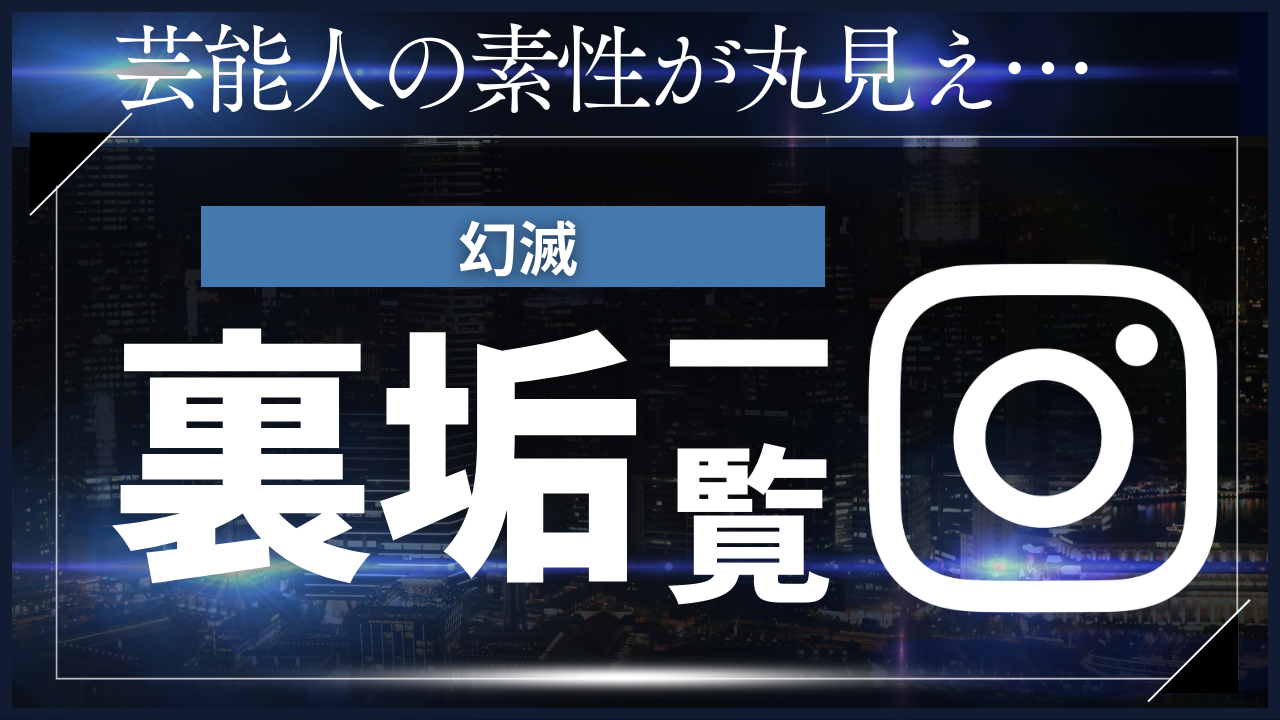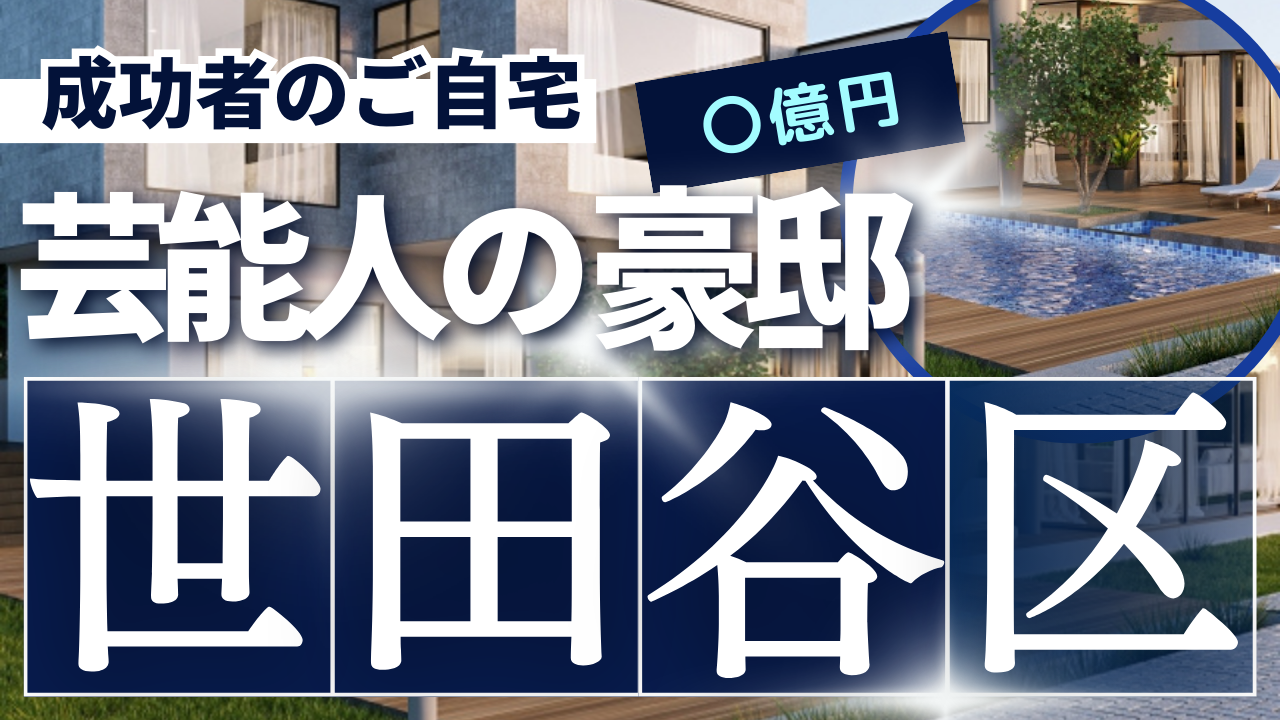人気ユーチューバー、水溜りボンドのノート炎上事件についてまとめました。心霊や宝探し動画が人気のさわやか大学生なカンタさんとトミーさんの二人組ユニットです。
水溜りボンドが、「フリクションボールペンで字を書いたノートをレンジでチンすると字が消える!」という内容の動画を出したのですが、これを真似した小学生がボヤ騒ぎを起こしたとして、その子の親がブログに書き、炎上。
しかも親の対応にも問題があったため、余計に炎上し、水溜りボンドが謝罪動画を出すまでに発展してしまいました。
そんな一部始終を問題のブログ記事の内容と共に詳しくまとめました。
水溜りボンドノート炎上事件と問題の親ブログについて
今回は、ユーチューバー側に注意喚起が足りなかったという部分と、親が子供のYouTube閲覧を管理していなかったという2点で大きく炎上したものです。
小学生が真似した水溜りボンドのレンジでノートをチン動画
フリクションのインクは熱に弱い性質があるそうで、熱を加えると文字が消えてしまいます。
今回はそれを利用して、「フリクションで書いたノートならば、レンジでチンして温めれば文字が消え、何度でも使えるようになるんじゃないか?」という検証を行った動画(現在は削除済み)でした。
私は実際にリアルタイムでこの動画を見ていて、実験は成功していました。
ノートの文字は消え、ページは真っ白になっており、再び新品のように使える状態になっていたので、「さすがだな~」なんて感心しておりました(笑)
小学生が鉛筆で文字を書いたノートをレンジで限界までチンしてボヤ騒ぎになる
この水溜りボンドのノート動画を見ていた小学生が真似をしました。600ワットで3分加熱した、と小学生は言っていたそうですが、おそらく何度も加熱したのではないかと。
実はこの小学生のノート、鉛筆で書かれていました。そのためどれだけレンジで加熱しても、字が消えることはありません。
「あれ、おかしいな、消えないなぁ」と思った小学生が、文字が消えるまでやろうとして、こんなにまでなってしまったと考えられます。
そして、小学生の父親はブロガーであったため、このノート炎上事件をブログに詳しく書き、合わせてユーチューバーを批判、問題点を指摘しました。
具体的に親のブログには、
「一見どんなペンで書いても消えると誤解されるようなタイトルでした」「タイトルだけ見るとあたかもすごい魔法のように大げさなタイトルになっています」
といった批判が書かれており、それによって息子が勘違いしてしまった、と記載されています。さらに、Youtuberの問題点も挙げており、
- ノートを電子レンジで加熱する危険性に関する説明が一切ない。
- 子どもの視聴者が多いと思われるにもかかわらず、「必ずお父さんやお母さんと一緒にやってください」という配慮がない。
- ワット数や加熱時間に関する具体的な情報が出てこない。(ノートを電子レンジに入れて「どう?そろそろいいかな?」みたいに話しているだけ)
- 扱いを間違えると今回のような事故が起きる可能性があるにも関わらず、「みんなもやってみてください!」という無責任な呼びかけで動画が終了している。
- そもそも電子レンジはノートを加熱するものではないので、そういう行為を不特定多数に向けて発信すること自体間違っている。
また、合わせて「動画を投稿した本人たちはそこまでの危険性があるとは自覚していない」と、Youtuberを叱責するような文章もありました。
水溜りボンドが謝罪動画を出す(サブチャンネル)
これを受けて、水溜りボンドはサブチャンネルで、謝罪動画を出しました。謝罪動画の中で2人は、
- 「真似しないでくださいという注意喚起が足りなかったこと」
- 「自分たちが子供に真似される立場という自覚が足りなかったこと」
- 「どのペンでもいいのではなく、フリクションボールペンだけだと伝えるのが足りなかったこと」
等を述べ、「すみませんでした」と謝罪しました。うーん、法に触れる行為というわけでもないし、別に公共の電波に乗っているテレビ局とは違うので、謝罪までしなくていいような気もしますが…。
さらに、このブログでは「『電子レンジで字が消える動画』は不思議でも何でもないことを息子に説明しました」等の記載もあります。
親ブロガーの自己反省点
小学生の父親は、今回の事件を経て、自分にも反省すべき点があったとしてこのようなものを挙げていました。
- 子どもたちが見ている動画(特にYouTuberが投稿している動画)は、くだらない物が多いなあと思いつつも、わざわざ厳しく注意したりすることはしなかった。(視聴時間を制限したりはしていたが)
- 今回は大事に至らなかったが、今回のようなケースでは最悪火事になったり、子どもたちが煙を吸い込んで病院に運ばれたりする危険性があった。
- 今思えば、今回子どもたちに説明したような話をちゃんとしておくべきだった。
事件当時、小学生はひとりでレンジを使ったそうです。
一応、家にはおばあさんがいらっしゃって、途中で異変に気付いて対処されたようですが、レンジ実験自体は、親が監督している状態ではありませんでした。
この一件があった後、「いったいどんな動画を見たんだ?」と思い、僕や妻もその動画を見てみました。
という記載があって、子供がどんな動画を見ているのか父親は把握していなかったようなのです。
「子どもの安全への配慮」を担うのはだれなんだろう?
確かに、水溜りボンド側にも注意喚起が足りず、うかつに薦めてしまった点が良くなかった、というのは言われている通りで、影響力がある分、その自覚をもって配慮をしてくれた方が良い、と感じる保護者の方もいらっしゃるのかもしれません。
しかし、「子どもの安全への配慮」というのはユーチューバー側が背負うものなのでしょうか?
多少の配慮をユーチューバー側に求める場合もあるかもしれませんが、第一次的にその責任を負うのは、親ではなかったのでしょうか。私は今回の炎上においては、その点が疑問でなりません。
Q.ジミヘンが音楽番組のステージパフォーマンスでギターを折り、その番組を見た子どもが真似をして父親のギターを折ろうとしてケガをしました。ジミヘンに配慮を求めるんですか?
ジミヘンは、派手なギターパフォーマンスをするミュージシャンです。ステージ上でギターを折ったりもします。
ジミヘンは世界的に大変有名な人物で、その影響力は並大抵のものではありません。もちろん、日本の学生ユーチューバーの影響力など、ジミヘンの影響力には到底及びません。
| そんな影響力のあるジミヘンのパフォーマンスを観て、「ぼくもやってみたい!」という衝動に駆られた小学生の男の子。家の中には、父親のギターが飾ってある。 ギターを手に取り持ち上げたところ、思ったよりもギターが重くて落としてしまった、運悪く自分の足の指の上に。 |
架空の事件を適当に作りました。
このとき、ジミヘンに「真似しないで下さい」って注意がなかったって怒るんですかね? 子どもが興味を持って真似するかもしれないのに「子どもの安全への配慮」がなかったと言うつもりなのでしょうか?
水溜りボンドよりも圧倒的に影響力のある人物なんだから、ジミヘンには、水溜りボンド以上に強い配慮を求めるべき、ってことになるんでしょうか? 変ですよね。
そうであれば、「影響力があることを自覚せよ」「危険性の説明が足りない」「子どもに対する配慮が欠けている」と言った批判は、どこの方向を向いているのでしょうか?
Youtube利用規約には「13歳未満の子供は利用しないで下さい」と書いてある
YouTubeの利用規約第12条を見てみると、年齢に関する記載があります。
12. 本サービス条件を受諾する能力
(前半部分 略)
本サービスは13歳未満の子供による利用を意図していません。あなたが13歳未満の場合、YouTubeウェブサイトを利用しないで下さい。あなたに、より適しているサイトが他にも沢山あります。あなたにそのサイトが適しているか、ご両親に相談してください。
また、Youtubeヘルプの「保護者向けリソース」にはこのような記載もあります。
YouTube を利用できる年齢
YouTube のアカウントを作成するには、13 歳以上であることが必要です。
「お子様が YouTube でどのようなユーザーと関わっているか把握しておきましょう。」
さらにはご丁寧に、保護者へ向けたこんなアドバイスまで明記されています。
親の監督責任とはいかに?
そもそもYoutube、13歳未満の子供はアカウントを作ることが禁止されています。したがって、視聴する場合は、親のアカウントを使って観るということになります。
今回の小学生は「13歳未満」でした。したがって、もしその子専用のアカウントを作っていたのであれば、Youtubeの利用規約違反です。
親が自分のアカウントを使って見せていたのであれば、自分の責任で子供たちが危なくないよう、監督すべきですよね。
これらの規約について一般ユーザーが指摘してさらに大炎上
元々のYoutubeを使うにあたってのお約束が、保護者は守れていなかったのです。
そのことが、ブログでみっちりユーチューバーに対する意見を書いて、さらにツイッターで水溜りボンドファンの反対意見にさんざん反論した後に、指摘されて判明したのです(笑) ここまで来てしまったら、後に引けませんよね。
そのブロガーはツイッターのアカウントと連携していたため、リプの嵐が巻き起こりました。大炎上です。
なんとあれだけハジけていた親ブロガーがだんまりを決め込む→さらにヒートア
利用規約の話が出てきてから、親ブロガーはだんまり状態になりました。おいおいww
それにより余計に水溜りボンドファン側がヒートアップしてしまい、嵐が大きくなり、やむを得ず途中で、リプをしてきた方々に謝ったようですが、水溜りボンドに謝罪したという話は一切ありません。
フタを開けてみれば、相手に「大人の対応」を求めていた張本人自身が、そもそも大人として守るべきルールを守れていなかった、という特大ブーメラン事案だったわけで、このような荒れ狂う形となってしまいました。
さすがに子どもが好きなものに対して「くだらない」は無い
いわゆる「世間一般的に良いとされるもの」「世間一般的に良くないとされるもの」を教えることは、教育として重要だという意見があるかもしれません。
しかし、それは親の価値観を植え付けてしまうことにもつながります。
親が「世間一般的に良いとされるもの」と思っていることは、実は「単に親が良いと思っているだけもの」に過ぎないことが多々ある、と考えるからです。
ここは人によって意見が分かれるところだと思うので、一概には言えません。ただ、子供が興味を持って楽しく観ているYoutubeの動画を「くだらないものが多い」と言ってしまうのは、子供に対して失礼な気が致します。
子どもを一人の人間として尊重したときに、そのような言葉は出てこないと思うからです。